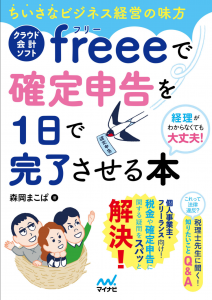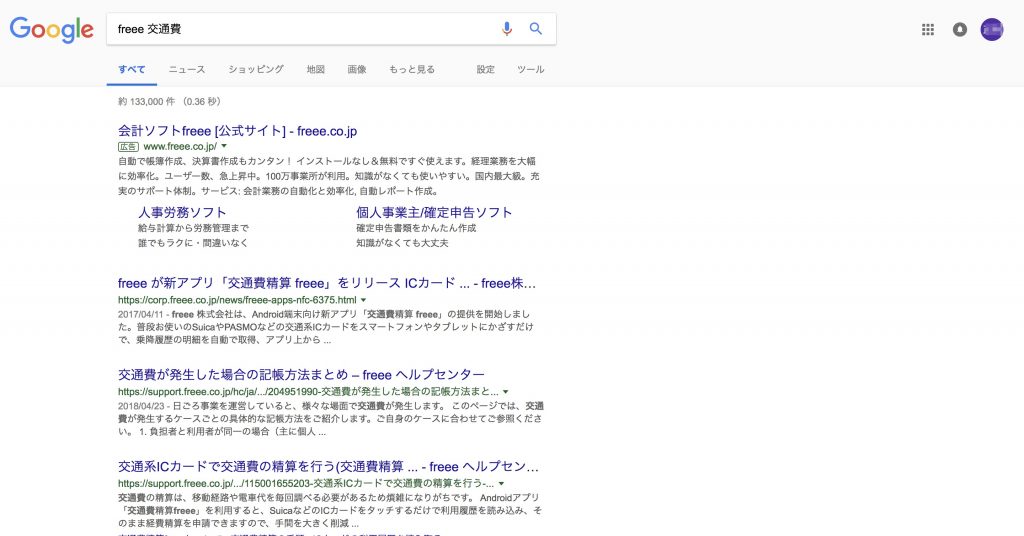はじめに 消費税の納税義務が生じた場合にはおおまかに分けてその計算方法が2通りあることはご存じだろうか。 一方は原則的な計算方法となっており、もう一方は特定の届出書を提出することによって適用を受けられる簡易課税制度となっ ... ]]>
はじめに 消費税の納税義務が生じた場合にはおおまかに分けてその計算方法が2通りあることはご存じだろうか。 一方は原則的な計算方法となっており、もう一方は特定の届出書を提出することによって適用を受けられる簡易課税制度となっ ... ]]>
はじめに
消費税の納税義務が生じた場合にはおおまかに分けてその計算方法が2通りあることはご存じだろうか。
一方は原則的な計算方法となっており、もう一方は特定の届出書を提出することによって適用を受けられる簡易課税制度となっております。
名前の通り消費税を簡易的に計算するのが簡易課税制度、厳密にそして煩雑は方法により計算をするのが原則課税となります。
ここでは原則的な計算方法、つまりは原則課税について触れて行きたいと思います。
消費税の計算方法(結論)
消費税の納税額については下記の算式により計算がなされます。
「課税売上に係る消費税 – 課税仕入に係る消費税 = 納税額」
ここではその計算の基礎となる課税売上に係る消費税と課税仕入に係る消費税について順に確認をしていきたいと思います。
【ポイント】
課税売上に係る消費税 = 課税売上高と連動しています。
課税仕入に係る消費税 = 仕入税額控除と連動しています。
課税売上高について
これは消費税の課税の対象となる資産の譲渡等(※注1)を行った場合における当該売上高のことを指します。
このためどのような収入が消費税の課税の対象となり、どのような収入が消費税の対象とならないのかを認識することが重要となります。
※注1…譲渡等には物の販売のみならず、サービスの提供などあらゆる取引を含めています。
【区分】
不課税
消費税は国内において事業の対価を得て行う取引に課税をするため、そもそも国外で行われた取引や寄付といった対価(見返り)の生じない取引について消費税を課税しないこととなっています。
非課税
こちらは国内において事業の対価を得て行う取引ではあるが、社会政策配慮の観点や課税対象になじまないものについて消費税を課税しないこととなっています。
免税
こちらも国内において事業の対価を得て行う取引ではあるが、一定の輸出等に関して消費税を免除するという規定となっております。
一件非課税と似てはいますが後述する「課税売上割合」や「仕入税額控除」に影響を及ぼします。
課税売上
上記以外が消費税の課税の対象と成る取引となります。
消費税の区分 | 消費税を含めるか否か | 例 |
不課税 | 消費税の対象外 | 寄付や贈与、国外取引等 |
非課税 | 消費税の対象外 | 土地や株の売買、預貯金の利子など |
免税 | 消費税は免除 | 一定の輸出など |
課税 | 課税の対象 | 上記以外の取引 |
課税売上割合について
読んで字のごとく、4つの区分の内課税売上高の割合がいくらであるかを算出したのが課税売上割合となります。
後述する仕入税額控除に大きな影響を与えるため非常に重要な論点となります。
【計算方法】
※分子・分母共に税抜の金額で計算
【ポイント】
- 不課税取引はそもそも消費税の対象外であるため分母・分子ともに算入されません。
- 非課税売上は社会政策上の配慮から消費税の対象外となっているに過ぎないため、全体の売上高(分子)には算入されます。ただ、当然消費税は課税されていないため分子には算入せずに課税売上割合を算出します。
- 免税売上については前提として「課税売上である。だが一定の輸出については消費税を免除する」という規定となっているため分母・分子ともに算入されます。
仕入税額控除に関して
当該規定については課税仕入を行った場合において、その課税仕入に係る消費税を前述の課税売上に係る消費税から控除するという規定となっております。
ただし、前述の課税売上割合に応じて計算方法が異なります。
【課税売上割合が95%以上の場合】
「全額控除」を適用
要約すると課税仕入に係る消費税の全額を課税売上に係る消費税から控除することが可能となります。
【課税売上割合が95%未満の場合】
この場合は「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のいずれかを選択して適用することとなります。
計算方法が煩雑であるためそれぞれ具体的に見て行きましょう。
個別対応方式
まず前提として課税仕入に係る消費税額の生じるすべての取引を下記の通り区分する必要がございます。
- 課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの
- 非課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの
- 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入等に係るもの
上記に区分した後、下記の算式に基づいて計算した金額が仕入税額控除の対象となります。
仕入税額控除 = ① + ③×課税売上割合
このように前提条件が非常に煩雑であり、そもそも区分をすることが非常に難しいため専門家指導の下でないとなかなか採用出来ない方法となっております。
そこで簡便的に計算をすることが可能となる制度が次の項目となる「一括比例配分方式」となります。
一括比例配分方式
こちらの計算方法は非常にシンプルとなっており、下記の通りとなります。
仕入税額控除 = 課税仕入に係る消費税額 × 課税売上割合
個別対応方式のように取引を区分する必要がなく、単純に課税売上割合を乗じるだけとなります。
計算がシンプルな反面2点程注意点がございます。
【注意点】
- 個別対応方式の方が有利となる場合がある
これは両方を比較した場合個別対応方式の方が有利となるケースがある点です。
前述の通り個別対応方式は事前に取引を区分する必要があるため初めから一括比例配分方式を選択しようと思って区分経理をしなかった場合、個別対応方式を選択できなくなってしまう余地が生じる点。
- 1度選択すると2年間は継続して適用しなければならない点
上記の通り一度選択をすると2年間は個別対応方式を選択することが出来なくなります。
そのため一括比例配分方式を選択する際には翌期の状況も見据えたうえで選択をしなければなりません。
輸入消費税がある場合の取り扱い
輸入を行う事業者ならご存じとは思うが、商品を輸入した際は税関を通じて関税及び消費税並びに地方消費税(以下、消費税)を納める必要が生じます。
ここで支払った消費税についても前述の仕入税額控除と同様に課税売上から控除することが出来ます。
消費税の記載がない場合の計算方法
請求書を受領したが消費税の記載がなく「請求金額10,000円」とだけ記載がされており、先方からは「うちは免税だから消費税を上乗せしていない」と言われることもあると思います。
果たしてこれはどのように取り扱えばいいか悩むこともあると思います。
ただし、このような取引であっても原理原則に従いその取引が不課税・非課税・免税・課税のうちどの区分に属するかを検討したうえで処理をしましょう。
たとえ相手が免税事業者であろうと、消費税は国内において事業の対価を得て行う取引であるため、この要件に該当したら消費税の課税の対象と成ります。
従って上記のような請求書を受領してもこれは「税込10,000円」と読み替えれば良い。
消費税率が10%であれば1.10で割り戻せばよいためこの例における税抜き価格は「10,000円÷1.1=9,091円」となる。
なお、1円未満の端数処理について切上げ・切捨て・四捨五入は任意で選択可能だかもし税抜価格を9,090円と計算した場合消費税が9,090円×10%=909円となってしまい合計額が10,000円に満たないという結果となります。
そのためここでは税抜9,091円として計算をしております。
インボイス方式に伴う今後の計算方法
このように「相手が免税事業はであるか否かに関係なく、取引の実態に応じて仕入税額控除を適用する」というのが今までの消費税の取り扱いでした。
ただし今後は消費税の大幅改正、適格請求書保存方式(インボイス方式)の導入に伴い上記のような取引は一掃されることとなります。
本格的な導入は2023年10月1日以降となりますが今の内から消費税の計算に多大な影響を与える制度が導入されることを留意しましょう。
終わりに
日常生活においては当たり前のように生じる消費税。
事業者の場合はこれらを預かる立場となるためこのように納税額の計算が非常に複雑となっております。
誤りが生じないよう正確にその取引がどのような区分に属するかを検討しましょう。
]]> ]]>
]]> はじめに 事前確定届出給与というものを聞いたことがあるだろうか? 会社経営をしている場合において大きな節税手段となりうる本項目ですが、その内容及び注意事項を正確に把握していないと逆に大きな損失を生じることとなります。 こ ... ]]>
はじめに 事前確定届出給与というものを聞いたことがあるだろうか? 会社経営をしている場合において大きな節税手段となりうる本項目ですが、その内容及び注意事項を正確に把握していないと逆に大きな損失を生じることとなります。 こ ... ]]> みなさんこんにちは。 この記事では、中小企業で適用できる、30万円未満の固定資産「少額減価償却資産」についてお話ししていきます。 備品等を購入した際、資産計上するよりも一括で経費にできた方が法人税の計算上お得になりますよ ... ]]>
みなさんこんにちは。 この記事では、中小企業で適用できる、30万円未満の固定資産「少額減価償却資産」についてお話ししていきます。 備品等を購入した際、資産計上するよりも一括で経費にできた方が法人税の計算上お得になりますよ ... ]]> はじめに 会社を運営していくにあたり必ずと考えなければならない資金繰り。 会社を設立した本人などに支払われる役員報酬はあらゆる面でこの資金繰りと直結することとなります。 何も考えずに役員報酬を支払うと法人税や所得税が想像 ... ]]>
はじめに 会社を運営していくにあたり必ずと考えなければならない資金繰り。 会社を設立した本人などに支払われる役員報酬はあらゆる面でこの資金繰りと直結することとなります。 何も考えずに役員報酬を支払うと法人税や所得税が想像 ... ]]> 経営セーフティ共済、聞いたことがない方は良い機会なので加入を検討してみてはいかがでしょうか。 共済の目的や内容がよくわからなくて、加入を躊躇されている方が意外と多いのではないかと思います。 経営セーフティ共 ... ]]>
経営セーフティ共済、聞いたことがない方は良い機会なので加入を検討してみてはいかがでしょうか。 共済の目的や内容がよくわからなくて、加入を躊躇されている方が意外と多いのではないかと思います。 経営セーフティ共 ... ]]> はじめに 我々の生活とは切っても切れない関係である租税の納税だが、中小企業法人(以下、中小法人)の場合果たしてどのような税金が課税されるのだろうか? ここでは中小法人が納めることとなる法人税等の種類及びその税率について解 ... ]]>
はじめに 我々の生活とは切っても切れない関係である租税の納税だが、中小企業法人(以下、中小法人)の場合果たしてどのような税金が課税されるのだろうか? ここでは中小法人が納めることとなる法人税等の種類及びその税率について解 ... ]]>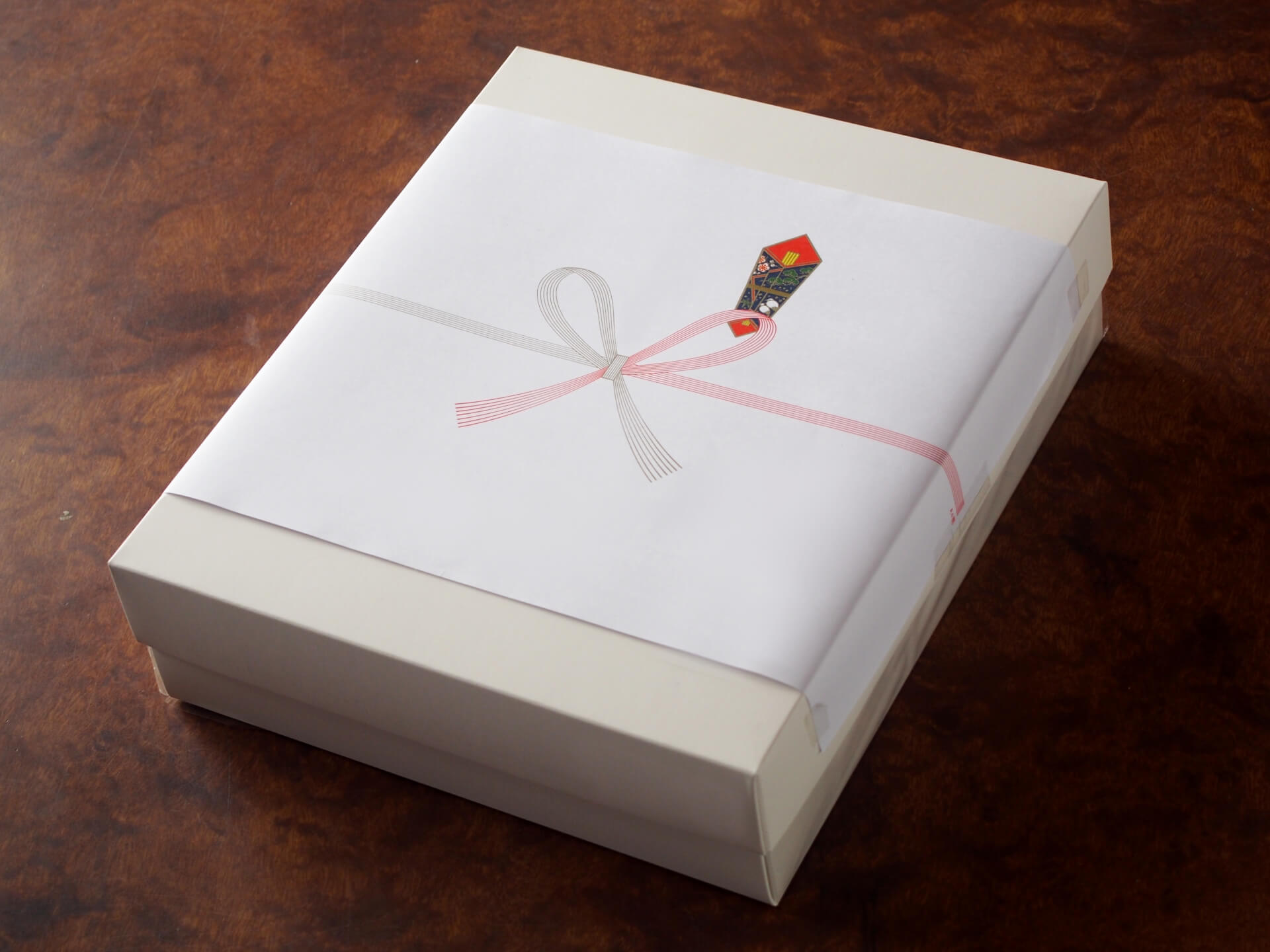 みなさんこんにちは。 この記事では、「交際費はいくらまでなら経費にできるのか?」ということについてお話ししたいと思います。 法人の様々な支出の中でも交際費は少し特殊で、経費として計上できる金額に上限があります。 そもそも ... ]]>
みなさんこんにちは。 この記事では、「交際費はいくらまでなら経費にできるのか?」ということについてお話ししたいと思います。 法人の様々な支出の中でも交際費は少し特殊で、経費として計上できる金額に上限があります。 そもそも ... ]]>


















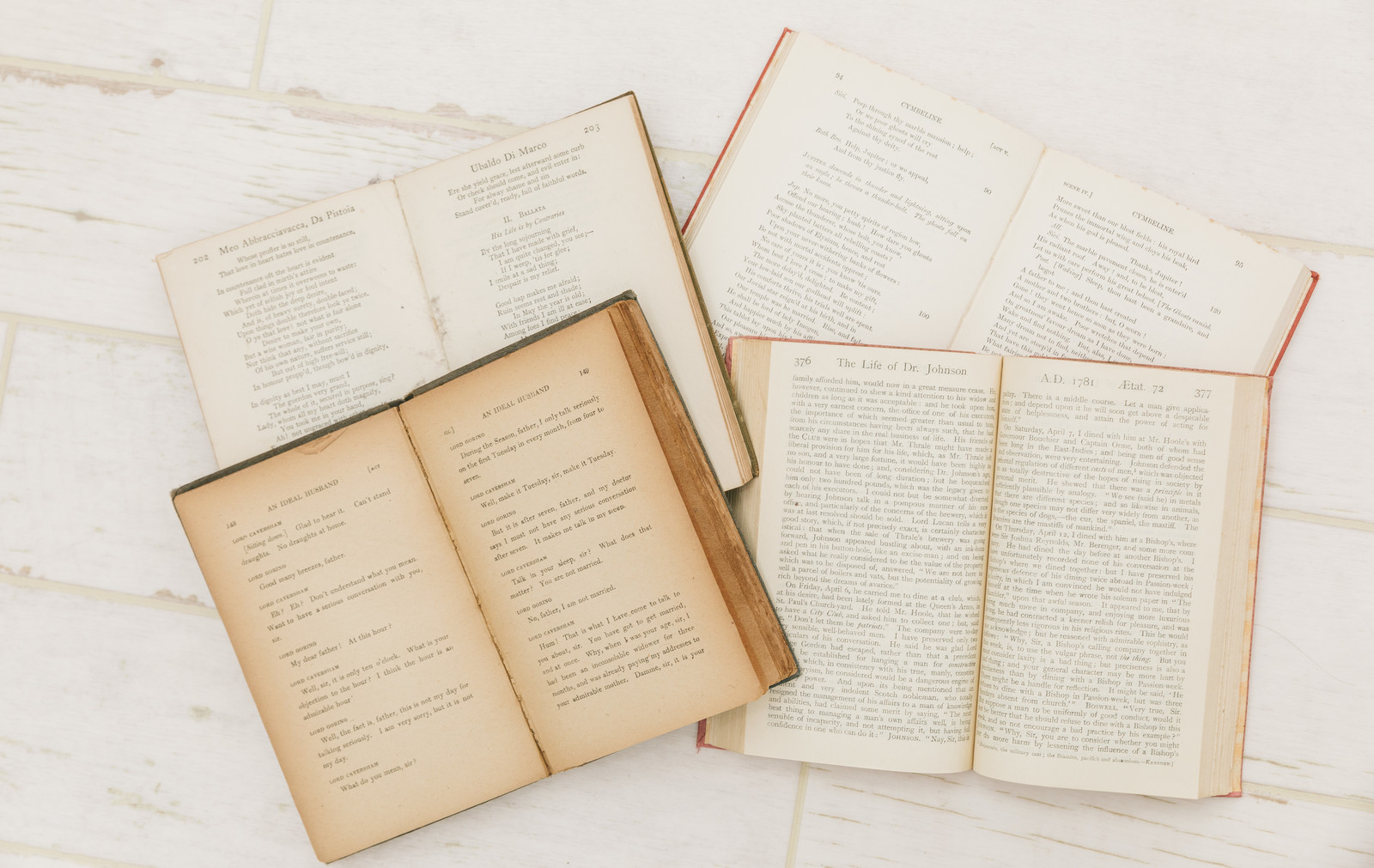 クラウド会計ソフトfreeeで経理をはじめることに決めた。 freeeの使い方がわからないのでおすすめの本があったら教えてほしい。 こんな疑問に答えます。 クラウド会計ソフトfreeeのおすすめ本 freeeの操作から税 ... ]]>
クラウド会計ソフトfreeeで経理をはじめることに決めた。 freeeの使い方がわからないのでおすすめの本があったら教えてほしい。 こんな疑問に答えます。 クラウド会計ソフトfreeeのおすすめ本 freeeの操作から税 ... ]]>